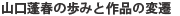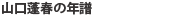山口蓬春の歩み
山口蓬春(本名・山口三郎)は、明治26年10月15日北海道に生まれました。父親の勤務に伴い明治36年に上京、中学校在学中には白馬会研究所で洋画を学びました。
大正4年東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋学科に入学後してからは、二科会において2度の入選を果たしますが、大正7年に日本画科に転科し、大正12年には首席で卒業しました。 8年間の学生生活を終えた蓬春は、師である松岡映丘が主宰する新興大和絵会に参加し、大正15年第7回帝展に出品した《三熊野の那智の御山》では、帝展特選、帝国美術院賞を受賞するとともに宮内庁買い上げとなり、画壇への華々しいデビューを飾ります。
しかし、新しい日本画の創造を目指した蓬春は、映丘と袂を分かち、帝展とも離れる試練の時期を迎えます。一方で、昭和5年福田平八郎、中村岳陵、木村荘八、中川紀元、牧野虎雄、横川毅一郎、外狩顕章らと六潮会(りくちょうかい)を結成。日本画家、洋画家、美術評論家からなる流派を超えた交流のなかで、独自の絵画領域を広げていきます。《市場》などの戦前の代表作をこの時期生み出しました。
 戦後は、新日本画への姿勢がより一層明確に打ち出され、ブラックやマティスなどフランス近代絵画の解釈を取り入れた知的でモダンなスタイルを確立します。《夏の印象》など明るく洗練された作品を発表し、日展を中心に活躍していきました。
戦後は、新日本画への姿勢がより一層明確に打ち出され、ブラックやマティスなどフランス近代絵画の解釈を取り入れた知的でモダンなスタイルを確立します。《夏の印象》など明るく洗練された作品を発表し、日展を中心に活躍していきました。
その後、《枇杷》などの緊張感に満ちた写実表現を経て、《紫陽花》などの清澄で格調ある表現へと画境を展開していきます。そして、代表作《春》《夏》《秋》《冬》を発表、昭和40年には文化勲章を受章しました。また晩年には、集大成ともいえる皇居新宮殿の杉戸絵《楓》を完成させました。
現状に甘んじることなく、常に新しい日本画の創造を模索し続けた蓬春は、多くの業績を残し昭和46年5月31日、77歳の生涯を閉じました。
作品の変遷
1. 新興大和絵会への参加
東京美術学校西洋画科に入学した蓬春は、君の絵は日本画の材料が合うのではないか、と評され悩んだ末、日本画科に転科する。そこで蓬春の指導に当たるのが、当時文展で活躍していた松岡映丘である。
この頃山口家は経済的に苦しく、蓬春は京都や奈良の名所絵を描いて生計をたてていた。生まれて初めて見る古都の風景に新鮮な感動を覚えた蓬春は《晩秋(深草) 》《秋二題 》など、叙情的な作風を見せる。
大正12年、東京美術学校日本画科を首席で卒業した蓬春は、映丘率いる新興大和絵会の同人となる。その後、第5回、第6回帝展への入選を経て、第7回帝展では《三熊野の那智の御山》が特選となり、帝国美術院賞をも受賞、作品は皇室買い上げという三重の栄誉を受けた蓬春は画壇への華々しいデビューを飾る。また、第8回帝展出品《緑庭》や第10回新興大和絵会出品《扇面流し》では、当時の大和絵が失っていた鮮烈な色調を復活させ、大和絵に近代的な命を与えた。
 《秋二題》 大正13年(1924) |
 《三熊野の那智の御山》下図 大正15年(1926) |
 《緑庭》 昭和2年(1927) |
 《扇面流し》 昭和5年(1930) |
2. 六潮会と個展時代
大和絵の形式を、今日の感情や思想に一致させる事は困難だと思う、と自ら述べた様に、蓬春は新興大和絵会の活動に限界を感じ始めていたようだ。
昭和5年、蓬春は六潮会に参加する。3人の日本画家と3人の洋画家、そして美術記者・批評家の8名から成り、流派を超えた自由な雰囲気の中、お互いが学び合うというこの会は、蓬春にとってはこの上ない研鑽の場となり、ここでの活動は以後10年間続くこととなる。そんな折り、蓬春は画壇の派閥の板挟みとなり、昭和10年に六潮会以外の全ての団体と訣別し、古典の模写に励みながら、昭和11年には初めての個展を開く。
大和絵の形式を取り払った蓬春は、馥郁たる自然を描いた《竹林の図 》や、江戸琳派の研究の跡が見られる《春汀》、隙の無いまとまりのある構成と衒いのない素直な描写によって表現された《泰山木》など、生き生きとした自然観照の姿勢を見せ、「一個の自由人となり、ひたすら自己の画生活の醇化に努力」していった。
蓬春は省略や強調の手法を交えた、新しい日本画を追求し始める。これは戦後、一気に開花する蓬春モダニズムの萌芽といってもよいだろう。
 《春野》昭和6年(1931) |
 《松原図》 昭和7年(1932) |
 《市場》 昭和7年(1932) |
 《春野》 昭和10年(1935) |
 《竹林の図》 昭和10年(1935) |
 《鶴》 昭和10年(1935) |
 《春汀》 昭和12年(1937)頃 |
 《泰山木》 昭和14年(1939) |
3. 南方に使いする
昭和13年以来、蓬春は美術展の審査員として毎年のように台湾や中国、南方の各地に赴いた。初めて目にする異国風景は蓬春にとって新たな創作力の源となった。
《南嶋薄暮》を取材した淡水(台湾の海港)について、「その建築の持つ絵画的な美しさは、西欧のそれも南仏か伊太利あたりの感じがあるのではないでしょうか。」と蓬春は述べており、南方の各地に見られる鮮やかな色彩に、殊に感銘を受けていたようだ。
一方、昭和10年代初頭の古典の学習以来、フォルムの単純化を一例とした画風の変化を見せていた蓬春が、戦後「蓬春モダニズム」と呼ばれるところの造形形成の過程を《残寒 》に見いだすことができる。省略や強調の手法を交えた、装飾的な画面は、終戦の到来を待てなかったようだ。
この頃、多くの画家が戦争に協力するよう求められていた。昭和17年、陸軍省から南方に派遣され、戦争画を描くことになるが、実際のところ、彼が心に抱いていたのは「今だ見ざる南方の新天地に対する思慕の念と憧憬」であった。
 《南嶋薄暮》 昭和6年(1931) |
 《残寒》 昭和17年(1942) |
 《九龍碼頭》 昭和18年(1943) |
 《瑞鶴》 昭和18年(1943) |
 《北京風景》素描 昭和18年(1943) |
4. 蓬春モダニズムの展開
昭和22年、蓬春は疎開先の山形・赤湯から帰り、葉山に移る。さらに、1年半後には現在の記念館となっている一色海岸近くに待望の新居を構えることになる。ちなみにこの画室は28年に同窓の建築家吉田五十八が設計したモダンな内装である。海に近いこの画室から夏の葉山の海岸を思わせるモチーフがたびたび登場することになる。
戦後の発表の舞台は日展が中心となり、第3回日展に出品した《山湖》が始まりであった。昭和20年代、日本画滅亡論が唱えられるころ、日本画は急速に西欧近代絵画を吸収する。そのなかで、蓬春は19世紀の以後のフランスを中心とした絵画に接近し、戦時の表現を払拭した新しい日本画を積極的にめざし、時代の思考や感覚をもとに近代の造形性を消化してゆく。漫然とした概念的な自然描写を排した表現や「もっと明るく、もっと複雑な、もっと強い、もっとリズミカルな」と言う蓬春の色感は、新鮮な画面を生み出している。
独特の造形感覚とともに、《望郷》にみられるようなしばしば卓抜した完成は、蓬春芸術のみせる大きな魅力でもある。こうした蓬春の作品は発表のたびに話題となり、明るく近代的な造形の追求は、"蓬春モダニズム"とよばれる世界を創り出した。
 《山湖》 昭和22年(1947) |
 《夏の印象》下図 昭和25年(1950) |
 《夏の印象》 昭和25年(1950) |
 《都波喜》 昭和26年(1951) |
 《卓上》 昭和27年(1952) |
 《望郷》 昭和28年(1953) |
5. 写実の時代
《山湖》から始まる実験的な風景画と、《夏の印象》などの構成的な静物画の近代的な形態と色彩による一連の作品は《望郷》が区切りとなった。その後の昭和30年代前半の一時期、蓬春は冷徹なリアリズムをめざす静物画を中心とした制作をおこなった。
「すべて写実が基盤になる、即ち写実主義(リアリズム)の基盤に立つのである。」と蓬春は述べている。自然観照から発想せよという蓬春の日常に向ける透徹した眼を感じさせ、なおかつそれが日本画として充分に消化されている。広がりをもたらす光の存在と、隈取りのように表現されている陰影が特徴であり、西欧的な静物画への傾斜を読みとることができる。
蓬春は画塾のような形態をとらなかったが、大山忠作、加藤東一、加倉井和夫、浦田正夫らが師事しており、こうした戦後の日本画壇を改革した若い原動力となった一采社の作家たちに大きな影響を与えたことも特筆される。同時代的感覚の導入と西欧近代絵画の吸収など、蓬春は戦後の次世代の画家に日本画のひとつの指針を示した。
 《鰊とピーマン》 昭和30年(1955) |
 《まり藻と花》 昭和30年(1955) |
 《冬菜》 昭和30年(1955) |
 《籠中春花》 昭和31年(1956) |
 《枇杷》 昭和31年(1956) |
6. 新日本画の創造
西洋画、古典大和絵から出発し、時代に即した日本画の創造を目指した蓬春。その画業においての最終的な課題は、和洋の真の融和であったといえる。
かつては大和絵の文学的抒情性から抜け出すために、人物や動物は画面から消し去られていた。蓬春は『新日本画の技法』の中で「構図の為に殊更に鳥を配置するようなことはせず、たとえ鳥が無くても、自然感の出るものは、強いて鳥を配する必要はない」「従来の花鳥画には、無理に不自然な鳥を配するような悪習慣がある」と述べている。
それが晩年に至り、《春》《夏》《秋》《冬》の連作を描き始めてから再び登場する小鳥の姿には、伝統的日本画の画題にあえて挑戦する蓬春の円熟した境地が窺えるようである。
現代の視点によって再び捕らえ直された花鳥画。同じモチーフにより繰り返し描かれた静物画。テーマを絞り込んだ晩年の作品では、岩絵具の清澄な色彩はますます深みを増し、洗練された構図と共に、近代的な明るさに満ちている。それこそ画家が独自に到達した新日本画の姿と見ることができるだろう。
「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない」
蓬春死後、美術評論家河北倫明氏はそう語った。蓬春芸術は、西洋画、日本画を超えた近代日本美術の一つの頂点ともいえるのである。
 《月明》 昭和35年(1960) |
 《宴》 昭和35年(1960) |
 《秋》 昭和36年(1961) |
 《春》 昭和37年(1962) |
 《冬》 昭和38年(1963) |
 《夏》 昭和40年(1965) |
 《楓》(皇居新宮殿杉戸絵4分の1下絵) 昭和42年(1967) |
 《陽に展く》 昭和43年(1968) |